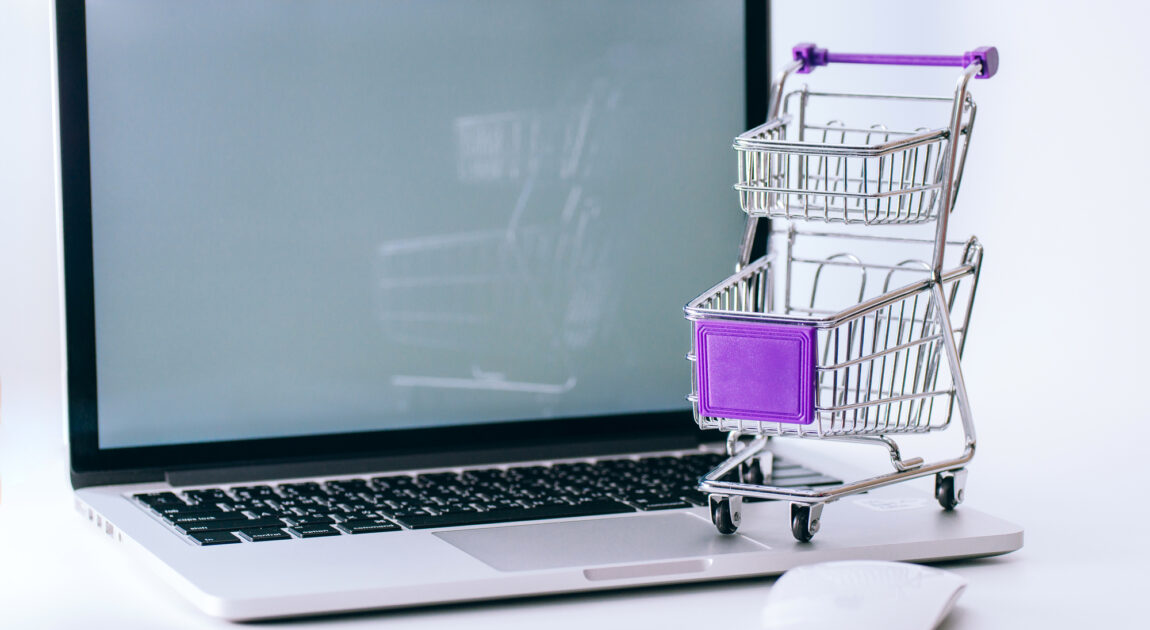経済産業省の令和6年度電子商取引に関する市場調査によると、2024年の日本のbtob領域におけるec化率は約4.3割と増加傾向にあります。 こうしたデジタル化が進む中で、「EDI」という単語がよく聞かれるようになりました。電子データのやり取りが可能になるEDIは、企業間取引の手間やコストを大幅に削減してくれます。 本記事では、従来型EDIやweb-EDIの概要や導入のメリット・デメリットについて解説します。
1.EDIとは何?
EDIは「Electronic Data Interchange」の略称であり、企業間で電子データの交換を行うことを指します。EDIを活用することで、従来は郵送やメール、FAXなどで行っていた書類のやり取りを、専用回線やインターネットを通じてシステム上で処理できるようになりました。さらに、やり取りしたデータを自動で取り込めるため、手作業を大幅に削減でき、取引先数の多い大手企業を中心に普及していました。
しかし今、EDIを取り巻く環境は、大きく変化しています。2024年1月にISDN回線のディジタル通信サービスが終了し、固定電話網を使用した従来のEDIが使用できなくなりました。現在は補完策としてメタルIP電話上でのデータ通信が提供されていますが、2028年12月31日で終了予定であり、通信速度不足や遅延も避けられません(参考:NTT東日本「INSネットをご利用の事業者さまへ」)。このまま旧来の仕組みに頼れば業務に支障が出る恐れがあり、早急にWEB受発注システムなどの新たな取引手段への切替の検討が不可欠です。
2.web-EDIとは?EDIとの違いは?
従来のEDIのサービス終了に伴い、代替先の候補として注目されているのが「web-EDI」です。では、EDIとweb-EDIとでは、一体どのような違いがあるのでしょうか。EDIの大きな特徴としては、電話回線を利用する点です。そのため、一般電話回線を利用するため通信費の発生や、通信の速度遅延などの難点があります。加えて、EDIは取引先によってソフトの使い分けが必要です。取引先が多い場合は処理に手間がかかりやすいという側面があります。企業によっては業務効率を向上させるためにEDIを導入したものの、かえって作業が煩雑になってしまったというケースも少なくありません。
一方、web-EDIは「Webサーバー上に構築されたシステム」を利用することが特徴です。Webブラウザなどのデジタル技術を用いて、インターネットを介して、システム操作やデータの送受信を行うことになります。Webサーバー上にシステムを構築し、ブラウザ上に表示した伝票イメージの画面で操作を行う「ブラウザ型」と、サーバーを介してファイル形式でデータをやり取りする「ファイル転送型」の2種類があり、商取引がより円滑に行える多くのメリットがあることから、多くの企業で導入が進んでいます。
3.従来のEDIはまだ使える?
結論、EDIはまだ使用可能です。2024年1月にEDIに用いられていたサービスの提供が終了していますが、補完策の代替サービスが2028年末まで提供される予定です。 すでにEDIを導入しており、現在も移行先を探している企業もあるでしょう。そもそも、従来のEDIは電話回線を利用する仕様上、前述の通りどうしても通信速度が遅かったり画像がうまく送れなかったりするなどの難点がありました。このような難点は業務の円滑化を図る企業にとって非常に大きな問題となっていたのです。この通り、従来型のEDIを利用している場合は、2028年末までにIP電話網や、受発注システムなどに移行する必要があります。つまり、今後のEDIにおける通信インフラは固定電話回線からIP網へと変更となり、従来のEDIを導入している場合は代替システムを至急検討する必要があります。
4.web-EDIの導入によるメリット
web-EDIを導入した場合、得られるメリットをご紹介します。
4-1.デジタル化で業務が効率化
web-EDIは、パソコンのブラウザを使ってシステムにアクセスします。これにより、企業間の商取引データをオンラインでやり取りすることが可能になります。取引書類が電子データとして送受信できるようになり、自動で基幹システムに取り込むことも可能です。 そのため、伝票や帳簿の印刷、確認の電話といった手間が不要になり、業務スピードの向上や担当者の負担軽減に大きく貢献します。
4-2.クラウド利用でアップデート不要
web-EDIは、より柔軟な対応が求められる中で、近年クラウド化が進んでいます。従来のEDIは導入時に、専用のソフトをパソコンにインストールするオンプレミス型で、導入時には手間がかかるものでした。さらに、円滑な運用には定期的にアップデートが必要で、パソコンの入れ替え時には、EDIが正常に動作するかどうかの確認も求められます。
その点、web-EDIはクラウドで提供されるため、システムの運用やアップデートは提供元に任せることができます。一般的なパソコンからブラウザを通じてログインできるため、スペックを気にせず操作できます。メンテナンスや維持にかかる負担を軽減できるでしょう。
4-3.コストの削減
Web-EDIを導入することは、業務にかかるさまざまなコストの削減にも役立ちます。たとえば、納品書や請求書などの書類をペーパーレス化できるため、紙やインク、封筒、郵送費といった印刷・発送にかかる費用を抑えることが可能です。
また、Web-EDIは専用ソフトや回線を必要としないため、導入時の初期コストも比較的抑えやすい点が特長です。
5.web-EDIの導入時のデメリット
web-EDI導入にはもちろんデメリットがあります。きちんとデメリットも確認したうえで導入を検討することが大切です。
Web-EDIを導入することで企業はいくつもメリットが得られる一方で、導入にあたっては注意しておくべきポイントもあります。従来型のEDIに対してweb-EDIは標準化がされていないため、受注側・発注側の両者でWeb-EDIを導入する必要があります。また、企業ごとにフォーマットが異なり、独自性の強いものも多いため、取引先ごとに異なるWeb-EDIに対応しなければならない場合があります。その結果、かえって業務の効率が下がってしまう可能性もあります。
そのため、Web-EDIを導入する際は、取引先との互換性や運用ルールの違いを事前に確認しておくことが重要です。特に注意したいのが、通信プロトコルと呼ばれる、データ送受信時のルールや手順の違いです。 主な通信プロトコルには、「EDIINT AS2」「OFTP2」「ebXML MS」「JX手順」「SFTP」「全銀協標準通信プロトコル」などがあり、取引先と異なるプロトコルを採用していると、連携に支障をきたす恐れがあります。そのため、複数のプロトコルに対応できるWeb-EDIを選ぶと安心です。
まとめ
従来のEDIを導入している企業であれば、今後は早急に切り替えを検討する必要があります。web-EDIは、企業の商取引をデジタル化し、コストや手間を削減できる便利な仕組みです。導入時や維持にかかるコストも安い傾向にあり、導入ハードルが低い点も魅力です。一方で取引先ごとに仕様が異なり、標準化が進んでいないという課題もあります。そのため、導入時には取引先との調整やシステム選定が欠かせません。
こうした背景から、最近ではWeb-EDIの利点を取り込みつつ、より直感的で使いやすい「受発注システム」を選ぶ企業も増えています。
受発注業務のデジタル化は『楽楽B2B』で対応可能
受発注をデジタル化するには、Web-EDIを活用するほかに、受発注システムを導入する選択肢もあります。 受発注システムを導入すると、ペーパーレスにより手作業が減り、受発注業務にかかる工数を削減できるため、処理漏れや転記ミスの防止にもつながります。 『楽楽B2B』は、受発注に関わる企業間の取引を効率化し、業務負荷を軽減できる受発注システムです。すべてのやり取りをシステム上で完結できるため、煩雑になりがちな受発注フローを効率化し、処理スピードの向上にもつながります。
また、BtoB EC機能を備えているため、複数取引先との少量多品種取引にも対応可能です。おすすめ商品の表示やキャンペーン施策など、販促と受注を一体で管理できるのも特徴です。見積発行や売掛決済、取引先別価格管理などの機能も備え、基幹システムとの連携により、企業間取引をさらに効率化できます。
『楽楽B2B』の詳細については、以下の資料をご確認ください。
▼楽楽B2Bの資料ダウンロードはこちら